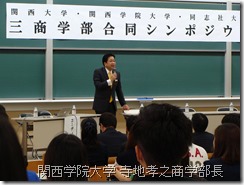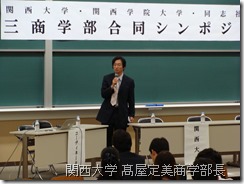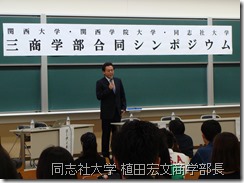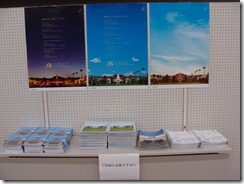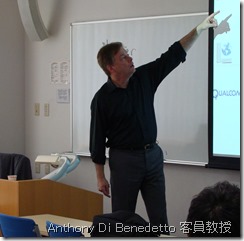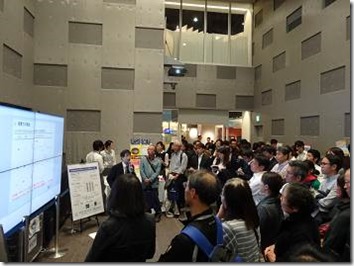« 2014年11月 | メイン | 2015年1月 »
2014年12月25日
第1回商学会懸賞論文の表彰式(12月17日)を行いました!
商学会は、今年度(平成26年度)から、商学部学生(個人もしくはグループ)を対象にして「商学に関する論文」(テーマは自由)の募集を始めました。
応募のあった論文は、厳正な審査の結果、優秀な論文に対して表彰状と賞金を授与します。
7月下旬から募集を開始した、第1回商学会懸賞論文の募集が10月31日(金)に締め切られ、個人・グループ合計13本の応募がありました。
応募のあった論文1本に対して、商学会に所属している商学部教員2名が審査を行いました。
厳正な審査の結果決定した、第1回商学会懸賞論文入賞者に対する表彰式を、平成26年12月17日(水)のお昼休みに、千里山キャンパス第2学舎1号館共通会議室において行いました。
当日は、高井准教授から審査の講評の説明の後、商学会会長(商学部長・商学研究科長)の杉本教授から賞状および賞金の贈呈がありました。
1等 : 井上裕貴さん・大澤和気さん・久保允誉さん・高田悠史さん
「プロダクト・プレイスメント効果の国際比較:日本と中国におけるオンライン・サーベイによる実証分析」
2等 : 川本有梨子さん・岡嶋良祐さん
「クロスボーダーM&Aにおいて国イメージとヒューマンバリューが買収後の製品イメージに与える影響」
3等 : 青木茉梨恵さん・岡田夏実さん・角本純太さん
「ブランド・パーソナリティ構造の国際比較」
佳作 : 山本崇之さん・牛尾絵美さん・北浦晴奈さん・武内里穂さん・永山美華さん
「中小企業の新規顧客獲得におけるWEB活用~大阪の中小製造企業の事例より~」
<表彰式出席者のみなさん>
なお、第1回商学会懸賞論文では、残念ながら「特賞」の該当論文はありませんでした。
商学会は、来年度も懸賞論文を募集する予定ですので、商学部生の皆さんはゼミの研究成果など、奮ってご応募ください。
☆写真をクリックすると写真が大きく表示されます。
情報提供 : 商学部 三谷准教授、岡准教授
2014年12月22日
三商学部合同シンポジウム(9月28日)を開催しました!
関西大学・関西学院大学・同志社大学の三商学部合同シンポジウム『商学部で学ぶことのプライド』が9月28日(日)15:00~17:30、西宮上ケ原キャンパスG号館101号教室において開催されました。
このシンポジウムは、関西学院創立125周年、高等学部商科開設100周年を記念して、伝統ある学部「商学部」の魅力を発信することが目的として開催されました。
当日は約150人の出席があり、関西学院創立125周年記念式典に出席後の、関西大学の池内理事長と楠見学長にも出席いただきました。
シンポジウムは、三商学部の学生、事務職員、学部長の三者により、3部構成で行われました。
【開会の挨拶】
関西学院大学の寺地孝之商学部長による開会の挨拶では、「伝統ある“商学部”の名称を現在も用いている大学は全国で9大学、関西では関西大学・関西学院大学・同志社大学の三大学のみであり、この三商学部が合同シンポジウムを開催するのは初めてであり、商学部で学ぶことの素晴らしさを発見するシンポジウムにしたい」という挨拶がありました。続いて、三商学部の学部長の自己紹介がありました。
【学生によるセッション】
三商学部の学生によるセッションは、幹事校の関西学院大学の学生2名が司会をつとめ、各大学から2名ずつの学生代表が登壇して「商学部で学ぶこと、商学部生であることのプライド」をテーマに、「なぜ商学部を選んだのか」「商学部で一番印象に残っている授業は何か」「商学部のプライドとは」についてそれぞれの学生が自身の考えや経験について紹介がありました。
商学部を選んだ理由について、「高校生の時から公認会計士を目指していた」「企業がどのようにして利益を出し続けるかなどに興味があった」と話していました。
また、商学部で、多様な知識を身につけることができた、社会人になったてすぐに役立つ知識を身に着けることができたという話のほかに、大学で受講した授業やゼミが就職する業界を決めるきっかけになったという話もあり、商学部で学んだことは人生を左右するほどの影響を受けた人もいたようです。
3大学の商学部生はいずれも満足度が高く、商学部生として学んだという「プライド」をもっていることがわかりました。
【事務職員からみた商学部生】
三商学部の事務職員からは、商学部生の特長や日々接している感想、今後の期待を述べました。
また、学生アンケート調査結果で商学部学生の満足度が高かったという発表もありました。
【学部長によるセッション】
三商学部の学部長によるセッションでは、「商学部の今を考える―商学部に何ができるか―」をテーマに、髙屋定美・関西大商学部長、寺地孝之・関西学院大商学部長、植田宏文・同志社大商学部長の討論が行われました。
「会計や金融など多様な分野を実践的に学べる」と共通する特徴を紹介し、「各大学の横のつながりを大事にして、商学部は古くさいというイメージを払拭していきたい」など、意見が述べられました。
商学部は、日本の大学でに9つしかなく、3商学部はそれぞれ多様なコース設定と特別なプログラムを提供していることがわかりました。
各学部長は、幅広く知識を習得させるのか、深く掘り下げて知識を修得させるべきなのか。ゼミを必修にするべきかどうか、必修にした場合の問題点など、教育の理想と現実の問題点などについての意見交換がありました。
商学部は、多様なカリキュラムを提供していて、幅広い知識を学ぶことができるのが特長であるが、広く浅く学ぶのか、深く掘り下げて知識を習得するのか、どちらも魅力があり、悩ましいということ。
ゼミを必修にすることは制度的に難しいが、商学部に限らず、大学に入学したからには「ゼミ」を履修し、「ゼミ活動」を体験して卒業して欲しいということが、3商学部の学部長の共通意見のようでした。
今回のシンポジウムをきっかけとして、3商学部がお互いに切磋琢磨して発展していけることを期待して、セッションは終了しました。
<3商学部の資料配付コーナー>
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
2014年12月16日
関西大学商学部学術講演会〔1月6日 池上 寬氏〕を開催します!
商学部、(社)日本物流団体連合会、商学会 共催の学術講演会を次のとおり開催いたします。
事前の申し込みは不要ですので、商学部生以外の方も奮ってご参加願います。
日 時 : 平成27年1月6日(火) 13:00~14:30(第3時限)
場 所 : 第2学舎 4号館 F402教室
演 題 : 「台湾における国際物流の現状と課題 ~グローバル化の中での変化~」
講演者 : 日本貿易振興機構 アジア経済研究所
新領域研究センター企業・産業研究グループ長代理
池上 寬 氏
講演会のチラシはこちら〔PDF〕をご覧ください。
| 台湾は日本と同様に島国であり、国際物流は海上と航空の2種類しかありません。1990年代にはコンテナ取り扱いでは第3位にランキングされる高雄港もありました。しかしながら、2000年代以降、中国の港湾の急速な発展により、その状況は大きく変化し、最近では高雄港のコンテナ取扱量は世界13位まで下がりました。 この要因の一つとして、台湾の製造業企業が海外進出することによって、産業の空洞化が起きたこと、また2008年12月まで、台湾と中国は直接航行をすることができなかったことが挙げられます。 今回の講演会では、台湾の概況も取り上げつつ、国際物流の現状と課題について最近の動向も踏まえてお話いただきます。 |
2014年12月13日
アンソニー・ディ・ベネディート客員教授が来日され、授業が始まっています!
関西大学商学部では、8月に招へいしたマーク・E・パリー客員教授に続き、2014年12月12日(金)~12月18日(木)まで、アメリカ合衆国フィラデルフィア州テンプル大学のアンソニー・ディ・ベネディート教授を客員教授に迎え、集中講義の形態で『 テクノロジーマネジメント』をご担当いただいています。
ディ・ベネディート教授は、アメリカのみならず、オランダ、イタリア、オーストリア、ロシアなどの各国の大学での講義経験が豊富で、日本語を含めた6ヶ国語を話されます。
これまでに100本以上の学術論文を公刊され、Great Minds of the 21st Century, Who’s Who Among American Teachers 等に名前が掲載されるとともに、ジャーナル・オブ・プロダクト・イノベーション・マネジメントという、経営学分野で世界のトップ10に入るジャーナルの編集長等、教育・研究の両面において顕著な活躍をされています。
商学部は、平成20年度入学生から「英語と会計に強いビジネスリーダー」を目指す新しいカリキュラムをスタートさせました。
今年で6年目を迎えるアンソニー・ディ・ベネディート教授の集中講義は、すべて英語で行われます。
ナチュラルスピードで授業をされていますが、ビジネスリーダー特別プログラム(BLSP)の主に3年次生(この授業の主な履修者30名)は、大変熱心に授業を受けています。
BLSPの第5期生である現3年次生は、春学期のマイクロソフト・プロジェクト、ワシントン大学とマイクロソフト本社で行った海外ワークショップ、秋学期の企業等とのプロジェクト等、プロジェクトゼミと英語の指導を受け、多彩なプログラムに挑戦してきました。
この1年間のビジネスリーダー特別プログラム(BLSP)の集大成として、英語と専門科目が融合したディ・デネディート教授の集中講義は、絶好の力試しの機会となっているようです。
ディ・ベネディート客員教授には、平成20-22年度文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」に採択された「英語に強いプロアクティブ・リーダーの育成」プログラムの1つであるビジネスリーダー特別プログラム(BLSP)」の講義担当およびプログラム・アドバイザーとして、ご協力いただいています。
☆写真をクリックすると大きく表示されます。
| 「英語に強いプロアクティブ・リーダーの育成」は、KUBIC(キュービック:Kansai Universiy Biz plan Competition)、CORES(コレス:CORE Skill Program)、BLSP(ビジネスリーダー特別プログラム:Business Leader Special Program)、BestA(ベスタ:Business English Study Abroad)という商学部独自の4つの教育プログラムで構成され、グローバル・ビジネスリーダーの育成をめざしています。 |
2014年12月 5日
関西大学文理融合プロジェクト:「こんなアイデア、どうですか?~食と技術とIdea~」を実施しています!
関西大学では、文理融合プロジェクトとして、理工系学部の研究成果を活かした新商品を商学部学生が提案! 企業関係者や一般来場者への試食とプレゼンテーションを行うというプロジェクトを実施しています。
このプロジェクトの一貫として、平成26年11月30日(日)、グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル2階のアクティブスタジオにおいて、イノベーション対話プログラムのプログレスワークショップ「こんなアイデア、どうですか?~食と技術とIdea~」を開催しました。
このワークショップの成果をもとに商学部学生は商品案およびビジネスプランをブラッシュアップをして、12月17日(水)15:00から、グランフロント大阪北館「ナレッジシアター」で最終発表会(ファイナルワークショップ)を開催し、商学部学生11チームのアイデアからチャンピオンを決定します。
アイデアから開発された試食品(数に限りがあります)をご用意します。
| 【12月17日(水)参加申し込み方法】 ○メール【申込アドレス】kenkyushien@ml.kandai.jp にて申し込んでください。 ・件名:「 12 月17 日ファイナルワークショップ参加希望 」 ・必要事項: ①氏名・②所属・③メールアドレス・④電話番号、を明記のうえお申込みください。 ※定員に達し次第受付を終了させていただく場合がありますのでご了承ください。 ※受付時にお名刺を頂戴いたします。 |
ファイナルワークショップの詳細については、次のURL(関西大学研究推進部ホームページ)に掲載しています。
http://www.kansai-u.ac.jp/Kenkyushien/kenkyu_shien/files/fws20141217.pdf
多くの方々のご参加をお待ちしております。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
秋学期より、商学部の2年次生向けに開講されている「演習」のCORESの一環として、文理融合型プロジェクトを商学部の荒木孝治教授、川上智子教授、西岡健一准教授の3ゼミで推進しています。
その内容は、関西大学化学生命工学部の河原秀久教授が開発された「接着タンパク質」という食物由来の安新・安全なエキスをシーズとして、3ゼミの学生チーム(計11チーム)が新商品の開発およびビジネスプランの作成を行うというものです。
このワークショップは中間発表会の位置付けで、その目的は学生が考案したレシピを基に連携企業が製造した試食品を、食品関連の企業関係者や一般消費者の方々に試食していただき、その際の対話を元にアイデアをブラッシュアップしていくことにあります。
各チームが最終的に1商品案に絞り、計11案が試作されました.スイーツや和菓子、パン、カレー、そば、介護食、非常食という多様な食品が試食に提供されました。
その試作品をベースに、専門家、企業関係者、一般消費者との対話を行いました。
また、河原教授による接着タンパク質に関するミニ講演も開催しました。
企業関係者や幅広い年代の一般参加者を含め、計200名以上に参加していただき、大盛況となりました。
今回の対話に基づき、学生は今後、商品案およびビジネスプランをブラッシュアップしていき、12月17日(水)にグランフロント大阪北館「ナレッジシアター」で最終発表会(ファイナルワークショップ)を開催します。
記事・写真提供 : 商学部 荒木 孝治教授