肢体不自由学生の支援
ご覧になりたい項目を選んでください。
肢体不自由とは
文部科学省は肢体不自由について、「肢体不自由とは、身体の動きに関する器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態をいう。肢体不自由の程度は、一人一人異なっているため、その把握に当たっては、学習上又は生活上どのような困難があるのか、それは補助的手段の活用によってどの程度軽減されるのか、といった観点から行うことが必要である。(教育支援資料,文部科学省初等中等教育局特別支援教育課,平成25年10月)」と定義しています。
つまり肢体不自由とは、①生活や学習に関する動作の困難であること、②様々な程度の困難があること、③実態把握にあたっては、支援などによって困難がどの程度軽減されるのかという観点が重要であること、④様々な身体部位における困難があること、⑤様々な医学的原因があること、をポイントに挙げることができます。
【参照】教職員のための障害学生修学支援ガイド(平成26年度改訂版) 日本学生支援機構
障がいのある学生からの質問
- 手指に障がいがあるため、筆記に時間がかかります。
また、両足にも障がいがあり、大学まで電車で通学することが困難です。
関西大学の合理的配慮の例を教えてください。 - 合理的配慮の内容については、学生相談・支援センター、所属学部・研究科、関係部署のスタッフ等を交えた面談のうえで決定されます。肢体不自由の学生に対して、関西大学では主に以下のような合理的配慮を行っています。
合理的配慮の例
車両の入構及び駐車許可
許可申請を行い、それが認められた場合に限りますが、大学内に自動車で入構し、許可された駐車スペースに車をとめることができます。
休憩室の利用
可能な範囲で、授業を受ける学舎内に休憩できる場所を用意します。
授業教室の調整
可能な範囲で、低層階の教室やエレベーターが利用できる教室で授業を行います。
ノート作成補助(代筆)
自分でノートをとることが困難な肢体不自由学生の代わりにノートを作成します。
支援メニューを利用している学生の声
代筆のおかげでスムーズに授業が受けられるようになりました。
法学部 法学政治学科 4年
(学年は2020年度当時)
私は重度の筋疾患を持っており、ほとんどのことが自分で出来ません。その為、学校生活はサポートがなければ不可能でした。でも、支援を活用することによって充実した生活を送ることが出来ました。
特に助かったのは授業時の代筆です。私は字を書くスピードが人より遅いため、授業で先生の話を聞きながらノートを取るということが出来ませんでしたが、学生支援スタッフの方の代筆のおかげでスムーズに授業が受けられるようになりました。また、支援だけではなく、スタッフの方は私にとてもフレンドリーな感じで接してくださり、同い年の方もいらっしゃったので、学校生活が楽しくなりました。
大学生活を振り返ってみて、改めて感じたことは、支援があったから4年間大学に通うことが出来たということです。学生支援スタッフや職員の方には感謝してもしきれないくらいです。
最後に、これから入学してくる、あるいは関大の受験を考えている障がいを持っていらっしゃる方へ。自分は障がいを持っているからといって、諦めないでください。充実した支援体制が関大にはあるのですから。あと忘れないで欲しいのは、自分をサポートしてくださる方に対する感謝の気持ちです。感謝をすればサポートしてくださる方も、気持ちよくサポートしてくださります。この気持ちがあれば、関大での4年間はとても充実したものになるでしょう。
周囲の人に知っておいてほしいこと
エレベーター
休み時間には多くの学生がエレベーターを使用します。
肢体不自由学生の中には、車椅子を使用するなど、階段での移動が困難な学生もいます。そうした学生は、エレベーターの利用者が集中する時間など、乗ることができずに授業に遅れることもあります。また、多くの学生が集中する場所では、車椅子の学生の存在が視野に入らず、ぶつかったりする危険性もあります。
階段を利用する、車椅子の学生のスペースを確保する、優先的にエレベーターが使用できるように順番を譲るなど、配慮しましょう。
多機能トイレ
多機能トイレは、車椅子を利用する学生をはじめとして、広いスペースや設置された設備を必要とする学生にとって、大学生活を行ううえで必要不可欠な場所です。
多機能トイレを長時間占有することは、多機能トイレでなければならない学生にとって、授業に遅れたり用を足せないなどの不都合が生じます。多機能トイレを必要とする学生の存在を意識し、不必要に占有することはやめましょう。
肢体不自由の学生とのコミュニケーションで心がけてもらいたいこと
- 車椅子に乗っている人や杖を使って歩く人にとっては、少しの段差や坂道が、大きな障がいになります。
場面に応じて、ちょっとしたサポートをお願いします。 - サポートには「見守り」という間接的な対応もあります。
必要に応じて、いつでもサポートできるように声やサインが届く距離で見守ることも大切な対応のひとつです。
「障害者差別解消法」が改正され、私立大学も合理的配慮の提供が義務化
2016年4月に施行された障害者差別解消法ですが、改正が行われ、2021年6月に公布、2024年4月に施行されました。
今回の改正点としては、これまで努力義務とされていた民間事業者における合理的配慮の提供が、義務化されたことがあります。これにより、私立大学も合理的配慮の提供が求められることになりました。
なお今回の改正では付帯決議が付されており、女性の障がい者や外国籍の障がい者など複合的な差別の解消や相談及び紛争の防止等の体制整備について言及されています。障害者政策委員会でも、間接差別や複合差別に関する相談事例を踏まえた適切な措置の必要性を求めており、大学としても今後の動きを注視しておく必要があります。
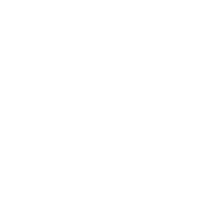 肢体不自由とは?
肢体不自由とは?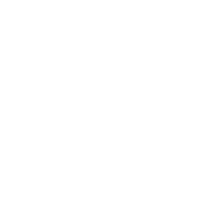 合理的配慮の例
合理的配慮の例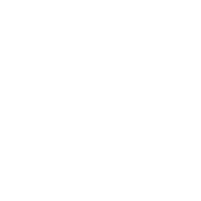 支援メニューを利用している学生の声
支援メニューを利用している学生の声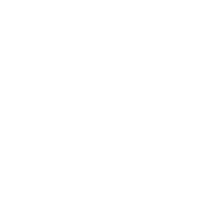 周囲の人に知っておいてほしいこと
周囲の人に知っておいてほしいこと